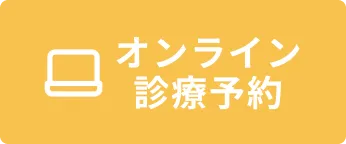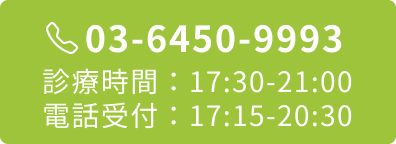
メンタルの不調
メンタルの不調を感じたら
最近、気分の落ち込みが続く、睡眠の質が悪い、意欲が湧かない…といったメンタルの不調を自覚していませんか?
それは、多忙な日々を送るあなたの心身が発している、重要なアラートかもしれません。
日々の業務や生活に追われ、ご自身のメンタルヘルスを後回しにしてしまうことは少なくありません。当ページでは、ご自身の状態を客観的に評価し、どのような可能性があるのかを知るための情報を提供します。

まずは客観的評価を – PHQ-9のご紹介
PHQ-9(Patient Health Questionnaire-9)は、現在の心の状態を知るための、世界中で使われている簡単な質問票です。専門家も利用するこの質問票を使い、過去2週間のご自身を振り返ることで、不調の度合いを客観的に把握する手がかりになります。
- これまで楽しめていたことが、楽しめなくなった。何に対してもやる気や興味がわかない。
- 気分が沈んで、ゆううつな気持ちになる。悲しくなったり、「もうダメだ」と希望が持てなくなったりする。
- 夜、なかなか寝付けない。夜中に何度も目が覚めてしまう。逆に、眠りすぎてしまうこともある。
- いつも体がだるくて、疲れやすい。すぐに疲れてしまい、エネルギーが湧いてこない感じがする。
- 食欲がなくなって、食べたくない。逆に、いつも以上にお腹がすいて、食べ過ぎてしまう。
- 「自分はダメな人間だ」「価値がない」など、自分を悪く考えてしまう。些細なことでも「自分のせいだ」と罪悪感を持ってしまう。
- テレビや本の内容が頭に入ってこない。仕事や勉強に集中できない。
- 周りの人から「動きや話し方がゆっくりになった」と言われる。または、じっとしていられず、イライラして焦る気持ちになる。
- 「いなくなってしまいたい」「死んでしまいたい」と考えてしまう。自分で自分を傷つけたくなってしまう。
この評価はあくまでスクリーニングであり、診断を確定するものではありません。しかし、ご自身の状態を把握する有用な指標となります。
詳しいセルフチェックはこちらをご覧ださい
うつ病症状のセルフチェックシートとは?治療方法も具体的に解説!
これらの症状はありませんか?
メンタルの不調は、気分の問題だけでなく、身体や普段の行動にも現れます。
気分の変化
- わけもなく憂うつな気分になる
- 常に不安や焦りを感じる
- ささいなことでイライラしやすくなる
- 集中力が続かず、物事を決められない
- これまで楽しめていた趣味が楽しめない
体の変化
- 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める
- 食欲が極端になくなる、または増える
- 頭痛や腹痛など、原因のはっきりしない不調が続く
- しっかり休んでも疲れがとれない
- 動悸、めまい、過度な汗といった体のサイン

行動の変化
- 仕事でのミスや遅刻が増える
- 人と会ったり話したりするのが億劫になる
- 身だしなみを気にしなくなる
- お酒の量が増える
- 感情の起伏が激しくなる

これらのサインが複数当てはまり、日常生活に影響が出ている場合は、一度専門家への相談をおすすめします。
考えられる精神の病気
メンタルの不調が続く背景には、以下のような病気が関係していることがあります。
- 自律神経失調症: ストレスや生活リズムの乱れから、身体のオン・オフを切り替える自律神経のバランスが崩れ、めまい・動悸・倦怠感といった様々な身体症状が前面に出る状態です。
- 適応障害: 職場の環境や人間関係など、特定のストレスが原因となって心身の不調が現れます。原因となっているストレスから離れると、症状が和らぐのが特徴です。
- 季節性感情障害(SAD): 日照時間が短くなる秋から冬にかけて気分の落ち込みなどが現れ、春になると回復するというサイクルを繰り返すタイプの不調です。特に、眠気が強くなったり、甘いものが無性に食べたくなったりすることがあります。
- 不安症(不安障害): 強い不安を主な症状とし、突然のパニック発作や、人前での過度な緊張、特定の物事への恐怖など、様々な形で現れます。
- 更年期障害: ホルモンバランスが大きく変動する時期に、ほてりやのぼせといった身体症状だけでなく、イライラ、不安、気分の落ち込みといった精神的な不調が起こりやすくなります。
ここに挙げたのは、あくまで考えられる病気の一例です。ご自身で判断するのは難しいため、気になる症状が続く場合は、一度専門医にご相談ください。また、メンタルの不調に似た症状が、甲状腺の病気など身体の病気によって引き起こされている可能性もあります。そのため、必要に応じて血液検査などを行い、原因を多角的に調べることが、適切な治療への第一歩となります。
なぜメンタルの不調は起こるのか?
メンタルの不調は、一つの原因だけで起こることは稀です。多くの場合、「からだ」「こころ」「環境」 という複数の要因が、パズルのように組み合わさって影響していると考えられています。
- からだの要因: 脳の働き、ホルモンバランスの変動、遺伝的な体質、身体の病気や疲れなどが挙げられます。
- こころの要因: 物事の捉え方(例:完璧主義、自分を責めやすい)、ストレスへの対処の仕方、もともとの気質などが影響します。
- 環境の要因: 職場のプレッシャー、家庭内の人間関係、経済的な問題、大きなライフイベント(例:昇進、離別)といった、自分を取り巻く状況がストレスになることがあります。
これらの要因が複雑に絡み合い、その人にとっての限界を超えたときに、不調としてサインが現れるのです。
一般的な治療アプローチについて
メンタルヘルスの治療では、一つの方法に頼るのではなく、その方の状態や背景に合わせて、以下のようなアプローチを組み合わせていくことが一般的です。
- 薬による治療
精神症状や身体症状による苦痛を緩和し、心身のエネルギー回復を促進するために薬物療法が選択されることがあります。抗うつ薬、抗不安薬、睡眠導入剤などを、エビデンスに基づき適切に処方します。薬物療法は、精神療法など他のアプローチに取り組むための土台作りとしても重要です。
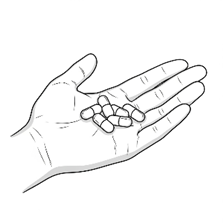
- 専門家との対話
医師やカウンセラーと対話を重ねる中で、ご自身の悩みや考え方のパターンを整理し、ストレスにうまく対処していく力を育てていくアプローチです。物事の捉え方の幅を広げる「認知行動療法」のような手法が知られていますが、まずは自分の気持ちを安心して話せる場所を持つこと自体が、回復の大きな助けとなります。

- 休養と環境調整
何よりもまず、心と体をしっかり休ませることが治療の基本です。ストレスの原因から物理的に距離を置く(例:休職する)ことも、時には必要です。安心して療養に専念できるよう、利用できる公的な支援制度(傷病手当金や自立支援医療など)について情報提供し、環境を整えるお手伝いをします。

一人で抱え込まず、専門家にご相談ください
メンタルの不調は早期に介入することで回復の可能性が高まりますが、放置すると症状が長引いたり、日常生活や社会生活への影響が大きくなったりする可能性があります。また、ご自身では気づかないうちに、身体の病気が隠れていることもあります 。気になる症状が続く場合は、一人で抱え込まず、ぜひ一度専門機関にご相談ください。当院では、メンタルの不調に悩む方が少しでも安心して治療に取り組めるよう、患者さま一人ひとりの生活スタイルに合わせた柔軟なサポート体制を整えています 。
- 通いやすい診療体制 平日夜間(17時45分から21時30分)まで診療を行っており、お仕事や学校帰りにも無理なくご来院いただけます。また、外出が難しい方や遠方の方のためにオンライン診療にも対応しており、通院の負担を減らしながら継続的な治療が可能です。
- 包括的なケア 心療内科だけでなく内科との連携も強化しており、睡眠障害の背景にあるうつ病などの精神的な問題や、関連する生活習慣病といった身体面の不調にも包括的に対応いたします。
- 長期的なサポート 治療の初期だけでなく、症状が改善したあとの「再発予防」や「生活の再構築」に向けた支援にも力を入れており、長期的な視点でのケアを大切にしています。
安心してご相談いただける環境を整え、皆さまの回復への一歩を、医師・スタッフ一同が丁寧にサポートいたします 。